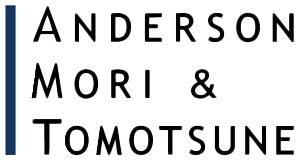心待ちにしていた本がついに出版された。著者の柏木昇先生は、言わずと知れた国際法務界の大家である。弁護士になりたてのころから先生のお書きになったもので勉強し、その後お知り合いになって情報・意見交換をするようになり、さらには先生が座長を務める日本法令外国語訳推進会議にメンバーとして加えていただいた。この小文のミクロな目的は、その学恩に感謝し報いることである。
いかなる専門分野も、後進が先人の成果を再検討しながら少しずつ歩みを進めることにより発展する。本書の真意や含意を理解するヒントになるかもしれない手がかりを、著者の後進であり若い法務・翻訳担当者の先人である者が残す――これが、この小文のマクロな目的である。
本書は、法令や判決文などの法律文書を英訳する場合の考え方について、著者の長年にわたる研究の成果をまとめたものである。テーマは幅広く、法律文書に限らない抽象的な翻訳論から、訳すのが難しい日本語の法律用語の訳し方にまで及ぶが、200ページ弱ときわめてコンパクトで密度が濃いため、理解が難しいところがあるかもしれない。そこで、あくまでも個人的に面白いと思った箇所に限るものではあるが、「見どころ」を説明しようと思う。なお、著者の言葉と私見とを区別するため、著書の言葉はページ数を入れて引用する。また、章名は本書のものをそのまま記載しているが、小項目名は小文独自のものである。
第1章 法律文翻訳の難しさと日本法令翻訳の黎明期の苦労
第1章では、法律文書翻訳についての著者版の「歴史」が語られる。その中にも、翻訳についての深い考察が随所に登場する。
本書の対象
本書は「法律文書」の「英訳」を検討する(12-13ページ)とのことだが、法律文書以外にも、和訳方向にも話が及んでいる。もちろん、説明上必要なのでそのような話題も取り上げているのだが、読者としてはその都度「居場所」と「方向」を確認しながら読むと理解が進むと思われる。小文がそのお役にたてば幸いである。
翻訳の目的
いきなりネタバレになってしまったら恐縮だが、「翻訳に関する判断決定は、その目的によって決まる」(20ページ)というのが、本書を通じての大きなテーマらしいことがわかる。このことが、以降さまざまな角度から論じられる。
第2章 法令や判例とその他法律文書の翻訳の目的の違い
第2章では、翻訳とは何か、何を目指すべきかが抽象論を交えて説かれる。
「等価」は等価か
著者は、翻訳論において"equivalence"という概念を「等価」と訳していることに疑問を呈していろいろと考察するが(27ページ)、結局「役に立たない概念である」と断じている(184ページ)。問題は「訳語」と「有用性」である。
まず、訳語として、「価」とは書いてあるが「価値」をどうこう言うわけではなく、要するに「等価」とは「おおむね同じであること」であると理解しておけばよいと思われる。言葉遊びになるが、"equivalence"と「等価」は等価だということでよさそうだ。
次に、「等価」という概念が翻訳を検討するにあたり有用かというと、やはり「役に立たない」と考えられる。翻訳は「等価」ならばよいといっても、「等価」という概念を間にはさんだだけで、「おおむね同じであること」の域を出ないからである。
余談だが、特許の分野に「均等論」という専門用語がある。これは"doctrine of equivalents"の訳で、ある技術が特許技術と同一でなくても「均等」と評価されるのであれば、その技術の実施は特許侵害になるという文脈で使われる。個人的にはこの訳語には違和感があり、そうお感じになる人も多いのではないかと思われるが、専門用語ではこういう意味であると理解するしかない。専門用語の翻訳とはそういうものである。
逐語訳、意訳、......
著者は、直訳、逐語訳、意訳、自由訳などについても疑問を呈し(30ページ)、これも最終的には、そのような区別は「不毛な議論である」と評している(42ページ)。各概念を明確に定義することは不可能で不要であろう。
「回り道」の意図
それでは、このように結論として意味がないとわかったことについて、なぜ著者は考察の過程を紹介しているのだろうか。それは、「読者が私のような回り道をしないように、翻訳理論理解に関する私の経験を書くことも重要ではないか」(はしがきiiiページ)との思いからである。
後進としては、「回り道」を教えていただくことにより、その回り道の途上で先人がどう考えたのか、さらに言えば、それは正しかったのかを含めて検証することができる。著者は後進に向けて誠実で親切な配慮を遣ってくれている。
契約書を「正確に」訳すとは
法令条文や契約書を翻訳する場合には、「原文に矛盾が含まれていれば、矛盾を温存したまま翻訳し、意味不明であれば意味不明のまま逐語訳をする」とされる(43ページ)。このような重要なことがさりげなく散りばめられているので、本書を読むときには注意が必要である。
たとえば、相手方から英文で提示された契約書を訳文によって検討する場合には、原文の過不足や問題点がありのままに明らかになっている必要があり、翻訳者が「かってに」意味を解釈して翻訳してしまってはいけない。(なお、この点につき微妙な問題があり、該当箇所(79ページ)で再検討することを予告しておく。)
『不実な美女か貞淑な醜女か』(米原万里、1994年)という、翻訳論の古典的な名著がある。現在では書名がコンプライアンス上問題であるなどと指摘されそうだが、発刊当時においては若干の衝撃を伴いながらも巧みな比喩だと評された。その中に、「何億という金の損得がかかっているような重要な商談の最中には、美しい訳よりも、日本語として響きがいいよりも、相手が何を欲しているのか、何で怒っているのかということが正確に伝わるほうが、遥かに大切」との名言がある。契約書はまさにそのような文書であり、「貞淑に」翻訳しなければならない。翻訳とは、「貞淑な美女」を追い求めつつ、文書の性質や翻訳の目的によって適当なところで折り合いをつける作業である。
意味不明な原文と訳注
意味不明な原文を意味不明のまま翻訳すると、訳文を読んだ人が翻訳者の力量不足ではないかと誤解してしまうおそれがあるので、原文の意味が不明であることについて訳注をつけることが勧められている(43ページ、84ページ)。翻訳を担当する立場の方々においては、実践するのがよいと思われる。
著者に問い合わせる
原文に意味がわからないところがある場合、その著者に問い合わせればよいとのことであるが(42ページ、83ページ)、実際問題としてそれができるか、そして適切かは慎重に考慮しなければならない。
法令の「著者」と言えるのは国会かもしれないし所管官庁かもしれない。しかし、それらが照会に答えてくれるか、そしてその答えに従えばよいかは保証の限りではない。意味が不明な法令はそれ自体が問題であり、翻訳で取り繕ってはいけないと思われる。判決を書いた裁判官が不明な判決文の解釈を教えてくれることは、ほぼあり得なそうである。一方、著作や論文では、著者に問い合わせることが可能な場合もあろう。
問題なのは、契約書である。たとえば、自社の営業担当者が書いた希望事項を法務担当者が英訳しているような場合であれば、著者に尋ねるのは容易だろう。しかし、契約の相手方が提示してきた案文に不明な箇所があった場合、それを尋ねるべきかどうかは、よく考えるのがよい。そのような迂遠なことをせずに、当方が有利と考える立場を明記した対案を返すほうが効率的かもしれない。
同じ用語は同じ訳語で
「ある特定の法律用語の訳語を使った場合には、その文書中で同じ意味を表すにはその同じ単語を使うべきである。」(45ページ)。これも法律文書を翻訳する場合の基本的な原則である。その応用が、のちに「解除」「解約」をめぐり具体的に説明されている(87ページ)。
(2)につづく
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.