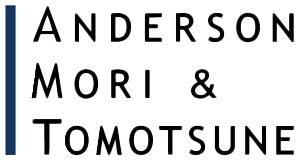第3章 言語の意味以外のファクター(文化、状況)と翻訳
第3章は、文書を「文字どおり」に訳すのではなく、背景を考慮すべきであるとの示唆から始まり、文化の違いを前提にした翻訳における注意事項に及ぶ。
「真意」を翻訳するか
「言葉は、その使われる状況によって意味が変わ」り、“Excuse me.”が状況によっては「何をボケッと通路を塞いでんのよ。どいてよ」を意味する(53ページ)。この場合の「真意」はそのとおりであるが、著者はそのように訳すべきだとおっしゃっているわけではないと思う。同じような状況であれば、日本語でも「ごめんなさい」で同じ真意を表せる。
一方、著者はある件において「善処します」を“I will do my best.”と通訳が訳し、その真意である“I won't do it.”と訳さなかったのは、翻訳としてはやむをえないと評している(76ページ)。この点は同感で、『新明解国語辞典』や『悪魔の辞典』のような解釈は「翻訳」とは言えないであろう。
閑話休題で、法律文書の翻訳においては、言葉とは異なる「真意」を訳すべきでないと考えられる。しかし、著者は面白い例を指摘する。法令中の「当分の間」を“until otherwise provided for by the law”と訳すべきではないかというのである(164ページ)。これはぎりぎりの難問だ。
コモンローの知識
正確に英訳するにはコモンローと比較法の知識が必須である(53ページ)とのご指摘はそのとおりであり、さらに、コモンロー系(英米など)ではなく大陸法系(ドイツ、フランスなど)の法律家向けであれば、その法系の用語(を英語にしたもの)を研究する必要がある。
しかし、現実問題としては、翻訳を担当する方々がこれを厳格に実行するのは困難ではないかと思われ、個々の法律用語について悩むたびに、その語を中心に少しずつ外国法の知識も勉強してゆくというところだろうか。第5章(95ページ以下)で紹介されている辞書や文献が大いに参考になる。
翻訳の目的
的確な翻訳は翻訳の目的を把握することから始まる――訳文の読者は誰か、訳注をつけてよいか、どのような文体がよいか、などである(62ページ)。これが本書の中心となるテーマだと思われ、このように随所に登場する。
第4章 「正確な翻訳」の誤解
第4章では、翻訳において「正確な」とはどういう意味で、どうすればそれに近づけるかが語られる。
当たらずとも遠からず
翻訳においては、要するに原語と訳語がどれくらい似通っていればよく、どれくらいの差異を認めるかという問題に帰着する。「当たらずとも遠からず」(70ページ)は至言である。
「抵当権」を“mortgage”と訳してよいか(71ページ)は著名な例であり、結論として“mortgage”で「当たらずとも遠からず」であろう。なお、暴論を覚悟で申し上げると、法制が国によって違うのは当然であり、英語を用いる国々の間でも、“mortgage”なる制度の内容は国によって異なる。とすれば、日本側からは「我が国の“mortgage”とは、こういう制度だ」というメッセージを出し続け、理解してもらえるようにすればよいのではないだろうか。これは「抵当権」に限らず、あらゆる日本の法律用語にあてはまる。この場合、大切なのは、ある語と決めたら一貫してその語で発信することであり、そのための手引きとして「標準対訳辞書」は有用なツールである。
語を補ってよいか
「正確に」訳すとは「意味不明であれば意味不明のまま」訳すことだとされているが(43ページ)、少し違うかもしれない例が挙げられている。
「原告は……手付けとして500万円を交付した」を“The plaintiff … paid 5,000,000 yen to the defendant as an earnest money.”というように、支払先(to the defendant)を補って訳すのがよいとされている(79ページ)。その理由は、「預託金としてでも、また、エスクローでもなく、売主に代金の一部として支払われたことを示すため」とのことである(80ページ)。
明記されていなくても支払先が一つに限られるのであれば、それを補って訳してもよいと思われるが、著者が指摘するような他のいろいろな可能性があり、また、仮に売買代金の一部だとしても、支払先は「被告」とは限らないのではないか。たとえば「被告の関連会社に対して支払う」という合意もあり得る。
法律文書とくに契約書を訳すときには、「意味不明であれば意味不明のまま」(43ページ)訳すことを厳しく徹底する必要がある。和文の契約書の中に、上に挙げた例文のような条文があったら、支払先を補わないで訳すべきだと考える。また、交渉中の契約書であれば、「誰に支払うのかが不明である」と問題を提起すべきである。
失礼を申し上げたかもしれない。読者の方々においてもご異論やご疑問があるかもしれない。しかし、このように議論することが、翻訳に対する姿勢を考えるきっかけとなり、翻訳の質を上げる手助けになると確信し、あえて“devil's advocate”(あまのじゃく)を演じた次第である。
第5章 標準対訳辞書にない法律用語の訳語の見つけ方
第5章では、法律用語の調査方法や参考書、訳語を決めるときの考え方などが示される。
外れずとも……
「不法原因給付」「取次」「問屋」などの英訳はいずれも難問である(100-113ページ)。英米法にない概念については、距離感を「外れずとも近からず」くらいでもよいと、寛容にとらえるしかないと思われる。
tsunami
英訳文中に日本語のローマ字表記を用いるのは避けるべきであるが(11ページ)、どうしようもない例もあるとして“tsunami”を挙げ、「自国語の文化にない言葉は、その意味を翻訳からではなく丸暗記的に理解するしかない」とする(111ページ)。これはそのとおりである。ただし、これはおそらく最後の手段で、原則としては何とか訳語を探す努力をすべきであることは言うまでもない。
(3)につづく
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.