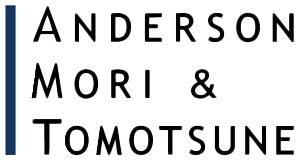多くのCIOは「書面・押印・対面」をなくしたいと思っているが、法務部は必ずしもそうではない。CIOは何に気をつけてこの問題に対峙すべきなのだろうか。
デジタル化で課題となる「書面・押印・対面」問題
2021年5月にはデジタル改革関連法が成立。6月18日には規制改革実施計画が閣議決定され、9月にはデジタル庁が発足。「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2022年6月7日閣議決定)では、「デジタル庁は、この国の⼈々の幸福を何よりも優先し、国や地⽅公共団体、⺠間事業者などの関係者と連携して社会全体のデジタル化を推進する取組を牽引」していくことを宣言。これを受ける形で行政の完全デジタル化とともに企業内でのデジタル化も急ピッチで進められている。
それだけではない。22年1月には改正電子帳簿保存法が施行され、電子帳簿等保存制度利用の際の事前承認の廃止や領収書や請求書のスキャナー保存要件の緩和など、電子帳簿等保存手続きの抜本的見直しが行われた一方で、24年1月からは電子取引での電子保存が義務化される。
さらに今年10月からは「インボイス(適格請求書)制度」が導入された。インボイス制度とは売り手が買い手に適用税率や消費税額等を知らせるという制度で、発行側も受取側もインボイスを保存する必要があり、書類の保存数はさらに増加。24年1月1日からの電子取引での電子保存の義務化を前に、経理の電子化に拍車をかけている。
テレワークの浸透や業務の効率化、企業の競争力強化などを進めていくためにはデジタル化は必要不可欠な取り組みであり、その恩恵も計り知れないものがある。
たとえばオンラインを使えば、遠隔地にいる人達と話をすることができるし、取締役会議事録も電子化されれば、海外にいる取締役がわざわざ署名(または記名押印)したものを日本の本社に郵送する必要はなくなる。数日かかっていた会議も1日で終えることができる。
株主総会は21年6月からバーチャルだけで開催することが可能となり、バーチャル総会を活用すれば株主もわざわざ株主総会の会場に出向く必要がなくなり、会社側も多くの株主が集まるような会場を探す必要がなくなる。
しかしその一方でITを活用するということは、サイバー空間への依存度が高まることから、サイバー攻撃やハッキング、なりすましなどのリスクは増す。企業の危機管理をしっかりとやりながら利便性の追求をCIOはしていかなければならない。
DXの最初の障害となるのが「書面・押印・対面」規制
そのような中でCIOはDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めていく上で、企業法務についてはどのように考えていかなければならないのだろうか。
DXに詳しいアンダーソン・毛利・友常法律事務所の宮川賢司弁護士は次のように語る。
「リーガルの分野の人間とCIOのようなシステムを担当する人たちとは、そもそも考え方が大きく違うのではないかと思います。たとえばCIOなどシステム開発の人間にとって文書の電子化というは当たり前のことですが、法務部などリーガルの分野の人間は、文書の証拠力を確保する観点から『書面・押印・対面』に強いこだわりを持っています」
法務DXを進めようとするときに最初に障がいとなるのが「書面・押印・対面」規制だ。20年以降規制緩和が飛躍的に進んでいるといわれているが、企業内でのデジタル改革の大きな障害となっている。
一般に契約は法令に特別な定めがないかぎり当事者の意思の合致によって成立するため、文書への押印は必須事項ではない。
契約書に押印するのは、契約の各当事者が押印することで後日紛争などになった際に契約が成立していることを立証することができると考えられているからだ。
最高裁判所の昭和39(1964)年5月12日判決でも「文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定する」としている。通常,印章(ことに実印)は厳重に保管されており、その所有者以外の者が勝手にこれを使用することは難しいと考えられているからだ。
そのため今までは疑問を持つことなく、大部分の会社が書面に押印していた。これをいざ、やめようとなると、法務の人間は「これ、裁判になったら大丈夫なのか」「個人情報は大丈夫なのか」「サイバー攻撃を受けたらどうすればいいのか」という不安がよぎる。
しかもすべてのビジネス文書が電子化されたわけではない。事業用の定期借地権設定契約、遺言などで活用される公正証書などは紙に押印しなければならないと法律で定められている。将来的には公正証書も電子化される方向で考えられてはいるが、完全電子化は2025年頃を予定している。銀行などにとっては口座名義人が死亡した場合に、本人の意思確認が厳格に要求されるものはまだ紙と印鑑を必要とする。
「不動産取引の重要事項説明書は電子化されたが、受け取り手が高齢者である場合は注意しなければならない。このほかにもいくつかルールがある。デジタル化をするにしても相手の理解度を確認しながら、進めていかなければなりません。労務管理の書類も、雇用契約(労働条件通知書)の相手方である従業員の承諾が必要です。そうしたところを法務部とシステム開発部が共同で検討していくことが重要です」(宮川氏)
大手5社が電子契約市場の70%を握る
電子契約の歴史を辿ると、2001年に電子署名を規定した電子署名法が施行され、両当事者が秘密鍵を保有し自ら署名を行う当事者署名型電子契約による電子署名がスタートした。
しかし当事者署名型契約は、契約の両当事者がサービス事業者の運営する電子認証局から本人確認を経て、電子証明書の発行を受ける必要があり、その費用も両当事者が負担しなければならないので手間とコストがかかる。
クラウドサインを運営する弁護士ドットコムの執行役員、小林誉幸氏は日本の電子契約の実情を次のように説明する。
「電子契約の法的効力を担保する電子署名は2000年に法制化されたのですが、当事者署名型契約は契約の相手方にも負担を強いる契約形態であるため、当初はなかなか普及していませんでした。それが大きく動き出したのは2015年です」
実はこのとき、民間のクラウドサイン、GMOサイン、ドキュサインの3社の事業者署名型電子契約サービスがスタートした。3社が選んだ事業者署名型電子契約とは両当事者が秘密鍵を保有せずに電子契約サービス事業者が立会人として電子署名を行うものだ。
「15年から緩やかに、利便性などをかっていただいたお客様から導入が広まっていきました。しかし当事者署名型でないことに法的効力の不安などがあり、労働条件通知書や賃貸借契約の重要事項説明書の電子契約が法律で禁じられていたことなどでなかなか急激に増加することはありませんでした」(小林氏)
その後電子契約が急速に伸びてくるのはコロナ禍に入ってからだ。テレワークなどが急増し、それに対応する必要が生まれたことに加え、主要省庁が連名で電子契約についての見解を発表したことが大きい。
20年6月19日の『押印についてのQ&A』では、押印に関する民事訴訟法上の取扱いや、押印の効果、押印を代替し得る手段等について、内閣府・法務省・経済産業省が連名で見解を発表。電子署名や電子認証サービスが文書作成の真正性の立証に関する手段の一つとなることを確認した。
さらに同年7月と9月に総務省、法務省、経済産業省が連名で事業者型電子署名についての電子署名法の適用についてもQ&Aを発表し、「個々の事案によるものの、事業者型電子署名の利用が二要素認証等により固有性の要件を充足すると認められる場合には、電子署名法第3条(電磁的記録の真正な成立の推定)の規定により、当該電子文書は真正に成立したものと推定されることとなると考えられる」(宮川氏)とした。
その後地方自治法施行規則や宅建業法が改正され、地方自治体や不動産取引でも電子署名が活用できるようになり、電子契約は一気に拡大した。
電子契約のサービスを提供しているのは現在、事業者署名型契約のサービスを提供しているクラウドサイン、ドキュサイン、GMOサイン、アクロバットサイン(旧アドビサイン)の4社サービスと当事者署名型電子契約のサービスであるコントラクトハブで、国内の電子契約市場の約70%(富士キメラ総研調べ)を占めている。
法人同士の契約では「なりすまし」と「無権限リスク」が課題
法人同士の契約の場合、電子署名で行うときのリスクは、「なりすまし」と当事者が権限を越えた契約をする「無権限リスク」があることだ。法人の代表者印(実印)があればこの2つのリスクはほぼクリア―できるといわれている。法人の代表印は厳格に保管されているので、他人がその印鑑を持ち出して勝手に押すということは簡単にはできないからだ。
通常の電子署名(例えば立会人型電子署名)の場合でかつ各担当者が会社のために電子署名をすることができる場合は、会社の担当者が権限ある状態で電子署名したことまで立証するのは難しい。
「電子メールのやり取りなども証拠として使うことができるので、そういったものを補強的証拠として合わせて利用することもありうるとクライアントなどには伝えています。ただそれも証拠としての価値はケースバイケースなので、万能というわけにはいきません」(宮川氏)
このほか外部統制機能を利用するというやり方もある。例えばワークフローシステムを例に考えてみよう。ワークフローシステムとは企業内で発生する申請や確認、承認といった手続きの流れを電子化・システム化したものだが、電子署名なども担当者が勝手にするのではなく、上司の承認がないと外部に発信できない外部統制機能を導入することが求められている。
リスクの低いものから順にデジタル化を推進
「書面・押印・対面」でやってきた仕事をデジタル化するにはどうすればもっとも効率的にできるのか。そして不正を未然に防ぐことができるのか。宮川氏は次のように語る。
「あまり便利にしてしまうと不正が起きやすくなってしまいますし、ハッキングなどのサイバー犯罪などの標的にもなりやすくなってしまいます。その点書面は、サイバー犯罪の標的にならないといえますが、偽造等の不正リスクはあります。結局のところ、契約の重要性等に応じて適切なリスク管理をすれば、電子署名でも書面押印でもあまり変わらないといえます」
データの保管などについても、クラウドで補完するのか、オフラインで管理するのか、書面で管理するのかでは、リスクの大きさが違う。
ではデジタル化を進めていくための優先順位をどうすればいいのだろうか。
「基本的にはリスクの低いものからデジタル化を進めていけばいいのだと思います。社運をかけるような重要な契約や個人情報が含まれるような契約をいきなりデジタル化してしまうと、ハッキングなどで莫大な損害が発生する恐れがあります。徐々に慣れていく必要があると思います」(宮川氏)
たとえば請求書一つ一つは仮にそれが盗まれたとしても大きな問題になるようなものではなく、むしろ請求書・領収書の数は契約書の数をしのぐといわれ、経理の電子化は経営の効率化に大きく貢献すると考えられている。
このほかグループ会社間の委託契約や法律事務所や会計事務所との顧問契約など当たり障りのない契約はすぐにデジタル化を進めても問題はないだろう。金額なども最初は1000万円以下のものから初めて、徐々に金額を上げていくといったやり方もある。
「仮に1億円以上の取引の場合は、もし相手がデジタルで契約をして『私は知りませんよ』なんて言い出したら、非常に困ることになる。したがって、重要な契約は慎重に進める必要があります。特許などのようなビジネスのコアになるようなものをクラウドで管理する場合には、相応のサイバー攻撃対策を行った上で進める必要があります。支障のないものから順次デジタル化していくことが重要なんだと思います」
初めて取引する相手などはお互い信頼関係がないので、最初のうちは書面で取引するという選択肢もあるだろう。
今後はAIなどのIT技術を活用して契約プロセスの効率化を図るリーガルテックに力を入れている企業が増えてくるという。
「書面を作ったりハンコを押したりするというのは実は契約の中で最後のアクションです。会社にとって一番大切なことはどのような契約を結ぶかです。これまでは弁護士や法務部担当者が自らの知識経験に基づいてアドバイスしていましたが、交渉の際に過去の契約データを使ってAIなどで分析し、最も効果的な方法を探して交渉するリーガルテックにも企業の関心が広がっています」
法律業務や手続きにIT技術を活用して新たな価値を提供するリーガルテックはこれまで、電子契約、AI契約書レビュー、リーガルリサーチ、翻訳、契約書作成、申請、出願などで活用されてきた。
しかし今後は契約レビューした結果として自社に不利な規定を削除・修正することを求める場合、相手を説得するための手段としても活用される可能性があるという。
「自社の主張を合理的に理由づけるために、過去の契約データ・マーケットにおける契約データ・裁判例・規制等をうまく使うことが効率的で、その際にもリーガルテックは役に立つと思われます。ただし、契約交渉はベテラン法務部員や弁護士の職人的スキルが必要ですので、経験なしには難しいかもしれません」(宮川氏)
Originally published by CIO.com.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.